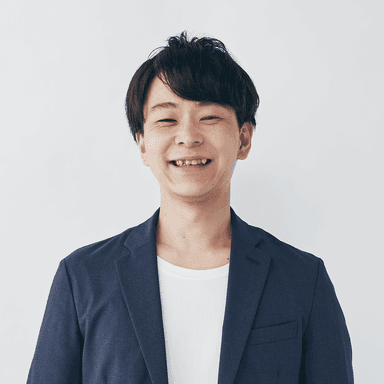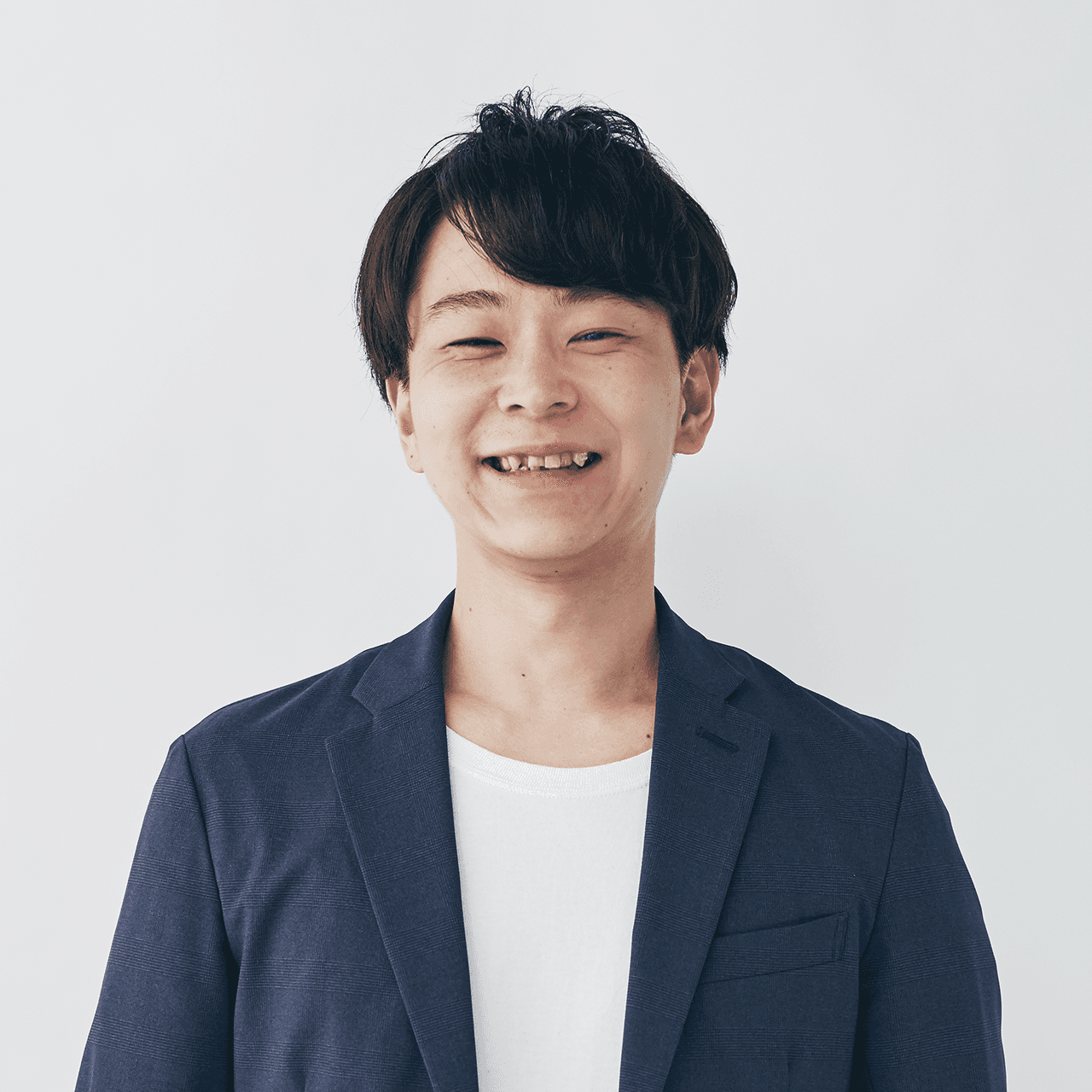直接CVを生まないコンテンツも、認知を獲得するための役割をもたせる
田島 光太郎
Marketing Planner / Consultant
想定場面や課題
コンテンツSEO施策において、全体のCVの約8割が、特定の2割のコンテンツから生まれることが多い。この偏りは、ユーザーの行動を「課題認知→情報収集→比較・検討→購入」の大きく4つのフェーズにカテゴライズした際に、購買行動に近いフェーズで閲覧されるコンテンツからCVが発生しやすいためである。
また、「認知フェーズ」で閲覧されるコンテンツよりも、購買行動に近い「比較・検討フェーズ」にカテゴライズされるコンテンツの量が少ないため、自然な構造である。しかし、すべてのコンテンツに同じレベルのCVを求めてしまうと、適切に役割分担されたコンテンツ設計ができず、リソース配分を誤るリスクが生まれる。
「課題認知フェーズ」のコンテンツでは直接的なCVは期待せず、認知・興味を醸成し、「比較検討フェーズ」にスムーズに移行させるための接点を作る。この設計思想を欠くと、短期成果に偏った施策運用となり、全体最適な成果創出が難しくなる。
重要なのは、ターゲットの購買行動プロセスに応じて、各コンテンツの目的と役割を明確に設計することである。
解決策
このような課題を解決し、成果を最大化するためには、カスタマージャーニーに基づき、フェーズごとの役割を明確に定義し、それに沿ったコンテンツ設計を行う必要がある。BtoBの場合、購買に近い「比較検討フェーズ」で、導入事例や比較コンテンツを通じて、直接的な問い合わせやトライアル申し込みに誘導する。
「課題認知フェーズ」では、CVを即座に求めるのではなく、認知・関心を高める施策を設計する。たとえば、課題解決型のホワイトペーパーを作成し、ダウンロードフォームを設置してリード情報を取得する。そのホワイトペーパー内にサービス紹介を組み込み、取得したリードに対してメールマーケティングやフォローアップなどのナーチャリング施策を展開する流れを作る。
このように、「課題認知フェーズ」では認知や興味を高め、次のフェーズに進むための基盤を整えることが重要となる。この区分を徹底することで、短期成果だけでなく、中長期の成果最大化を目指した施策運用が可能になる。
決して、「比較検討」か「課題認知フェーズ」のどちらかを攻める、という話ではなく、認知から検討、購買に至る各接点で必要な役割を果たす設計により、コンテンツごとの最適配置とリソース投下の精度を高め、オウンドメディア施策全体の成果を底上げするための戦略である。