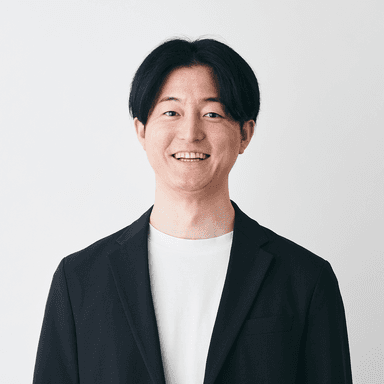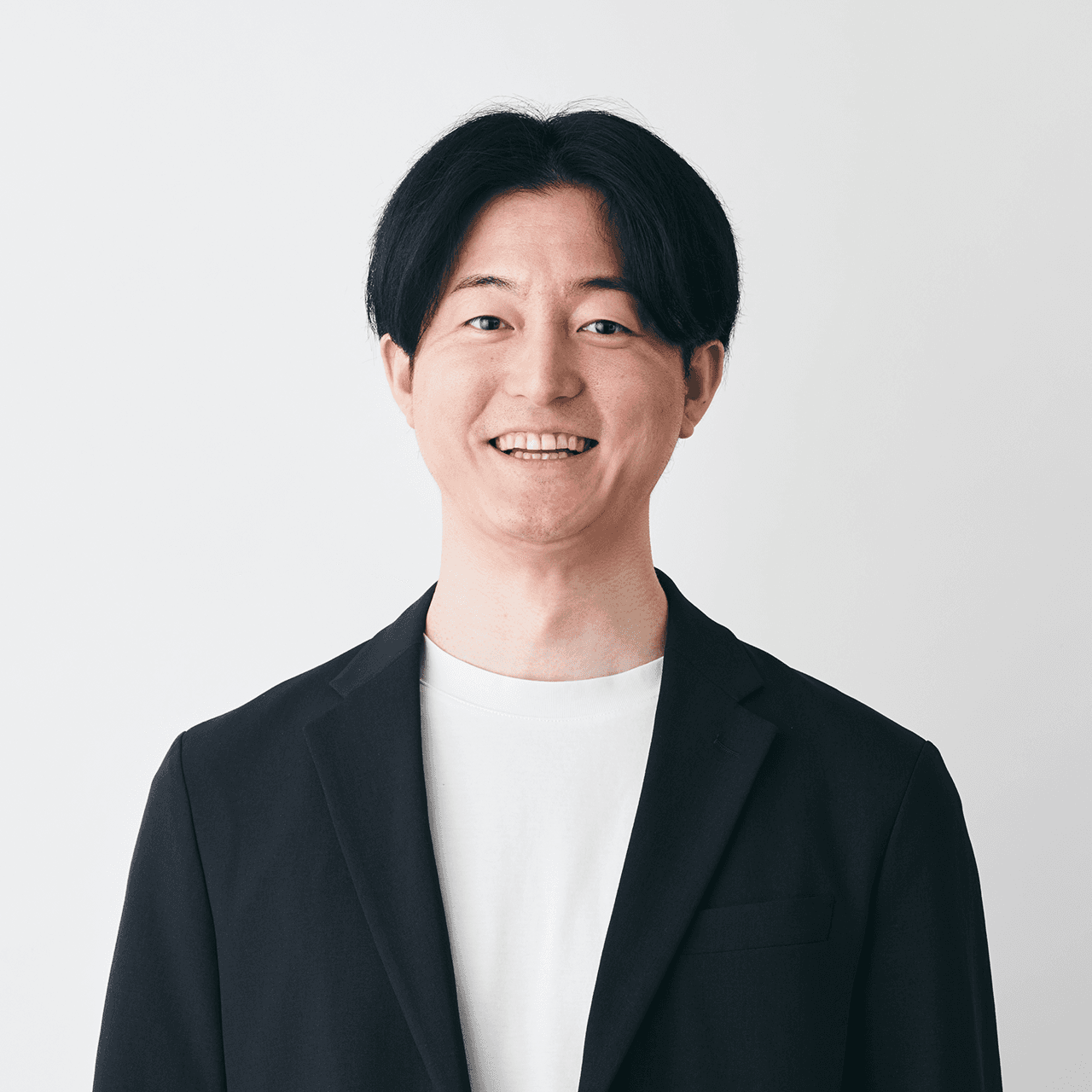リソース不足や不安を乗り越え、小規模チームで成果を出す方法
岸 晃
Marketing Director / Consultant
想定場面や課題
新しいサービスを立ち上げたり、既存サービスの方向性を変えたりするときには、「限られたリソースで早く成果を出すこと」が求められる。特に小規模なチームでは、1人で多くの業務を抱えることになりやすく、さまざまな課題が浮かび上がる。
「やるべきことが多いのに人手が足りない」「どこから手をつければいいのか」「本当にこのやり方でいいのか」といった不安もつきまとう。メンバーの間で情報量や経験の差があると、チーム全体で進むべき方向がバラバラになり、モチベーションにも差が出やすい。
これらの問題の根本にあるのが、優先順位のあいまいさだ。何を最初にやるべきか、どこを削るべきかが見えないまま進めると、チーム内で混乱が起きる。また、実績がない段階では「このまま進んでいいのか?」という不安が消えない。
このような状態を放っておくと、成果が出せずにプロジェクトが止まったり、メンバーのやる気が下がって組織全体のエネルギーが失われたりする可能性がある。
解決策
この課題を解決し、小さなチームでも短期間で成果を出すには、まず「誰が・何を・いつまでにやるか」を明確にし、チームで合意形成からはじめる。役割分担と優先順位をはっきりさせ、全員で合意した上で動き出すことで、共通認識を持ったうえでリソースを無駄なく使える。
次に、「小さく始めて早く検証する」ことが重要だ。最初から大きな成果を目指すのではなく、すぐに測定できる目標を設定し、それに対してどんな結果が出たかを確認しながら進める。これにより、方向性が合っているかどうかを早い段階で見極められる。
さらに、気づいたことはどんなに小さくてもチーム内で共有することが大切。
例えば、
・全員の朝会やチーム定例などで、シェアする時間を必ず確保する
・疑問点や不明点は、全員がいる場で解消する
・情報を共有してくれた人に、全員が見えるSlackのチャンネルで感謝を伝える
・なるべく一つ一つコメントやリアクションを返す
・失敗は絶対に責めない、ポジティブなコメントで返す
など。
うまくいったこと、失敗したこと、気になったことをオープンに話し合うことで、情報の格差がなくなり、全員が同じ目線で進めるようになる。特に成功体験は、チーム全体で喜びにすることで、モチベーションアップにつながる。
この方法は、心理的安全性を生み出す効果もある。情報が共有される環境では、上下関係にとらわれず、自由に意見を出せるようになり、自然とチームに一体感が生まれる。実際にこのやり方を取り入れた現場では、メンバー同士の距離が縮まり、気づきや改善点がスムーズにやり取りされるようになった。
その結果、小さな成功が積み重なり、プロジェクトが前向きに進んでいく流れをつくることができた。